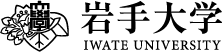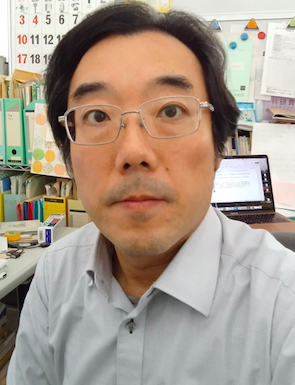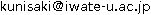|
所属 |
岩手大学 農学部 地域環境科学科 森林科学コース |
|
職名 |
教授 |
|
生年 |
1971年 |
|
研究室住所 |
〒0208550 岩手県 盛岡市上田3-18-8 |
|
研究室 |
森林動態制御 |
|
メールアドレス |
|
國崎 貴嗣 (KUNISAKI Takashi)
|
|
|
学内職務経歴 【 表示 / 非表示 】
-
2024年01月-継続中
岩手大学 農学部 森林科学科 教授 [本務]
-
2007年04月-2023年12月
岩手大学 ■廃止組織■ 共生環境課程 准教授 [本務]
-
2005年11月-2007年03月
岩手大学 農学部 農林環境科学科 森林科学 助教授 [本務]
-
2000年12月-2005年10月
岩手大学 農学部 農林環境科学科 森林科学 講師 [本務]
-
1997年04月-2000年11月
岩手大学 農学部 助手 [本務]
可能な出前講義 【 表示 / 非表示 】
-
カブトムシの樹皮剥ぎと生態系エンジニアリング [一般・高校生向け]
講義の概要
-
森林の状態を数字で捉える [一般・高校生向け]
講義の概要
森林を構成する樹木の樹種、樹齢、サイズの組み合わせによって、森林の姿は異なります。一方で、細かい質的情報を無視して、単なる数字1つで表現しても、森林の状態を意外と正確に把握することができます。講義では、森林の「混み具合」に注目し、「いかに簡単な調査によって1つの数字で表すか」を模索する森林科学研究の世界を紹介します。
担当授業科目 【 表示 / 非表示 】
-
2022年度
海外・日本の林業
-
2022年度
卒業研究
-
2022年度
森林計測学実習
-
2022年度
森林計測学
-
2022年度
自然環境保全論
指導学生数 【 表示 / 非表示 】
-
2024年度
卒業研究指導(学部):1人
学位論文審査(学部・主査):1人
研究指導(修士・主任指導):1人
研究指導(修士・第2副指導):1人
学位論文審査(修士・副査)/ 教育実践研究報告書審査(副担当):1人
【連合農学研究科・連合獣医学研究科】 第2副指導(博士):1人
-
2023年度
卒業研究指導(学部):4人
学位論文審査(学部・主査):4人
研究指導(修士・第2副指導):1人
学位論文審査(修士・副査)/ 教育実践研究報告書審査(副担当):1人
-
2022年度
卒業研究指導(学部):6人
学位論文審査(学部・主査):4人
研究指導(修士・主任指導):1人
研究指導(修士・第2副指導):2人
学位論文審査(修士・主査)/ 教育実践研究報告書審査(主担当):1人
-
2021年度
卒業研究指導(学部):7人
学位論文審査(学部・主査):2人
研究指導(修士・第1副指導):2人
研究指導(修士・第2副指導):1人
学位論文審査(修士・副査)/ 教育実践研究報告書審査(副担当):2人
-
2020年度
卒業研究指導(学部):6人
学位論文審査(学部・主査):3人
FD 研修・教育研究会における発表 【 表示 / 非表示 】
-
博士課程教育における指導のあり方
教育研究会名 : 岩手連大教員資格取得者研修会(FD講演会)
開催年月 : 2023年10月
-
デジタルトランスフォーメーション時代の反転授業を考える
教育研究会名 : 岩手大学全学FD研修
開催年月 : 2021年08月
-
令和2年度学生支援を考える教職員FD・SD研修会
教育研究会名 : 令和2年度学生支援を考える教職員FD・SD研修会
開催年月 : 2021年03月
-
新しい時代の教養教育を考える
教育研究会名 : 岩手大学全学FD研修
開催年月 : 2020年08月
-
国立大学法人岩手大学ハラスメント防止研修
教育研究会名 : 岩手大学ハラスメント防止委員会
開催年月 : 2019年12月
その他教育活動の特記すべき事項 【 表示 / 非表示 】
-
2011年度
学生生活指導活動
研究室配属学生2名の指導
-
2011年度
進路指導業務
研究室配属学生の指導にあたった。
-
2011年度
教材及び授業等で取り入れた特記すべき事項
生物統計学,森林資源と人間生活I,森林資源と人間生活II,森林計測学,森林計画学で,質問要用紙を配布し,可能な限り多くの質問を吸い上げ,理解度を確認した。
-
2010年度
学生生活指導活動
研究室配属学生4名の指導
-
2010年度
進路指導業務
研究室配属学生の指導にあたった。
研究経歴 【 表示 / 非表示 】
-
人工林の針広混交林への誘導技術
研究期間:
1999年04月-継続中研究課題キーワード : 森林構造、樹木種多様性、競争,地形
研究態様: 個人研究
研究制度: 民間学術研究振興費補助金
研究活動内容
1999年以来,大学演習林内にスギ人工林固定試験地を設定し,継続調査を続けている。
-
同齢単純林のサイズ構造動態
研究期間:
1997年04月-継続中研究課題キーワード : 同齢単純林、サイズ構造、競争
研究態様: 個人研究
研究制度: 科学研究費補助金
研究活動内容
1997年の着任以来,若齢および高齢スギ人工林に固定試験地を設置し,継続調査している。また,2004年からは広葉樹人工林の成長特性を調査している。
-
二次林の森林動態
研究期間:
1997年04月-継続中研究課題キーワード : 成長量,サイズ構造,樹種組成
研究態様: 個人研究
研究制度: その他の研究制度
研究活動内容
1997年の着任以来,アカマツ二次林,コナラ二次林,サワグルミ二次林について林分構造を調査している。サワグルミ二次林については,岩泉町の協力を得て,町有林内に固定試験地を2003年に設置し,継続調査している。
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Habitat selection by chestnut-cheeked starling during the breeding season in the northern Tohoku region
Oizumi R., Ikeda K., Kunisaki T., Yamauchi K.
Ornithological Science ( The Ornithological Society of Japan ) 24 1 - 11 2025年04月 [査読有り]
学術誌 共著・分担
-
Cross-sectional area increment of the lower trunk in aged Sugi (Cryptomeria japonica) trees: A heightening trend
Kunisaki T,Yoshida S
Journal of Forest Planning 30 1 - 9 2024年04月 [査読有り]
学術誌 共著・分担
-
過密なスギ人工林における間伐効果ー樹冠長と胸高直径成長量に基づく分析
國崎貴嗣,白旗学,松木佐和子
日本森林学会誌 104 ( 4 ) 223 - 228 2022年08月 [査読有り]
学会誌 共著・分担
-
過密なスギ人工林における樹冠長と直近5年間の胸高直径成長量との関係
國崎貴嗣,白旗学,松木佐和子
日本森林学会誌 103 ( 6 ) 401 - 404 2021年12月 [査読有り]
学会誌 共著・分担
-
過密なスギ老齢人工林における41年間の林分成長経過
國崎貴嗣,山崎遥
日本森林学会誌 103 ( 4 ) 285 - 290 2021年08月 [査読有り]
学会誌 共著・分担
著書 【 表示 / 非表示 】
-
田中和博,吉田茂二郎,白石則彦,松村直人,國崎貴嗣,他多数(数十名) ( 担当範囲: 第4章2節 針葉樹人工林の管理と施業(のうち14ページ分) )
朝倉書店 2020年04月 ISBN: 978-4-254-47055-0
教科書
-
施業の集約化における林分配置の目標林型の設定:作業級の設定に学ぶ
國崎貴嗣
日本造林協会 2016年10月
一般雑誌・新聞への寄稿
-
天然更新(前更)作業による広葉樹林化の課題:ケヤキの育林プロセスを例に
國崎貴嗣
日本造林協会 2016年06月
一般雑誌・新聞への寄稿
-
天然更新(後更)作業における初期保育の重要性:天然生林の再生に向けて
國崎貴嗣
日本造林協会 2016年03月
一般雑誌・新聞への寄稿
総説・解説記事 【 表示 / 非表示 】
-
粗放的に管理された岩手県内針葉樹人工林における強度間伐後の低木層の発達過程
國崎貴嗣
岩手大学農学部演習林報告 ( 岩手大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター ) 53 49 - 62 2022年06月
大学紀要
-
粗放的に管理されたスギ人工林における成熟段階での複層混交林化
國崎貴嗣,吉川秀平,橋本卓拓
岩手大学農学部演習林報告 ( 岩手大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター ) 55 19 - 41 2024年06月
大学紀要
-
エゾエノキで樹液獲得するカブトムシの個体群動態
國崎貴嗣
岩手大学農学部演習林報告 ( 岩手大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター ) 56 27 - 41 2025年06月
大学紀要
-
コナラ高齢天然生林の皆伐後3年目におけるコナラ稚樹の個体群構造
國崎貴嗣
岩手大学農学部演習林報告 ( 岩手大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター ) 56 43 - 51 2025年06月
大学紀要
研究発表 【 表示 / 非表示 】
-
間伐前後における森林土壌の透水・保水性の変化
ポスター(一般) 松本一穂,渡部優,髙田乃倫予,高野涼,伊藤幸男, 國崎貴嗣, 山本信次, 原科幸爾
第136回日本森林学会大会 (名古屋)
2025年03月日本森林学会
-
胸高帯のみかけの低下に及ぼす傾斜度の影響:スギ若齢林での事例
口頭(一般) 國崎貴嗣
第131回日本森林学会大会 (名古屋)
2020年03月日本森林学会
-
八幡平のオオシラビソ疎生林の更新機構:林冠・ササ条件による光環境および実生・稚樹の生残・成長のちがい
口頭(一般) 杉田久志・西尾悠佑・高橋利彦・梶本卓也・市原優・國崎貴嗣
植生学会第23回大会 (宇都宮大学峰キャンパス)
2018年10月植生学会
-
アカマツ天然生林皆伐後3年目における高木広葉樹の加入・再生状況
口頭(一般) 國崎貴嗣
第129回日本森林学会大会 (高知)
2018年03月日本森林学会
-
無間伐のスギ若齢人工林における樹冠長率と幹成長量との関係
ポスター(一般) 國崎貴嗣
第127回日本森林学会大会 (藤沢)
2016年03月日本森林学会
学術関係受賞 【 表示 / 非表示 】
-
森林計画学会 黒岩菊郎奨励賞
2011年03月
受賞者: 國崎貴嗣(宮沢俊一,本間多恵子,青井俊樹と共著) Effects of canopy tree characteristics and forest floor vegetation on defication site selection of a Japanese serow (Capricornis crispus) population in lowland managed forests in northern Japan
上記の業績は、スギ林とアカマツ林,広葉樹林が混在する森林地帯におけるニホンカモシカ個体群の環境選択性を,森林構造特性から解明しようとしたもので、特にスギ林について新たな知見を提示している。この成果は野生動物管理に貴重な示唆を与えるもので、学術上・応用上の価値が大変高いと認められる。
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
スギ高齢林の材積は過小推定なのか?:幹形と断面積成長に基づく新たな材積式の調製
基盤研究(C)
代表者: 國崎 貴嗣
支払支給期間:
2024年04月-継続中獲得年度・受入金額(円)・間接経費(円)
2024年度・ 650,000円・ 150,000円
2025年度・ 390,000円・ 90,000円
2026年度・ 520,000円・ 120,000円
-
刈り出ししない刈り払い「筋残し刈り」を用いた省力的天然更新作業の開発
基盤研究(C)
支払支給期間:
2017年04月-2021年03月獲得年度・受入金額(円)・間接経費(円)
2017年度・ 500,000円・ 150,000円
2018年度・ 200,000円・ 60,000円
2019年度・ 200,000円・ 60,000円
2020年度・ 200,000円・ 60,000円
-
刈り払いは控えめにーケヤキ稚樹の生残と樹形発達に与える雑草木切除の効果
基盤研究(C)
支払支給期間:
2012年04月-2015年03月獲得年度・受入金額(円)・間接経費(円)
2012年度・ 900,000円・ 270,000円
2013年度・ 700,000円・ 210,000円
2014年度・ 800,000円・ 240,000円
-
新たな手法による野生動物の生息地利用及び被害防除システムの構築に関する研究
基盤研究(B)
支払支給期間:
2009年04月-2013年03月獲得年度・受入金額(円)・間接経費(円)
2009年度・ 400,000円・ 0円
2010年度・ 200,000円・ 0円
2011年度・ 100,000円・ 0円
2012年度・ 50,000円・ 0円
-
野生動物による農林業被害発生機構の解明と被害防除法に関する実証的的研究-被害多発地におけるツキノワグマの生態および個体群特性と生息環境の質的検討-
基盤研究(B)
支払支給期間:
2005年04月-2009年03月獲得年度・受入金額(円)・間接経費(円)
2005年度・ 0円・ 0円
2006年度・ 0円・ 0円
2007年度・ 0円・ 0円
2008年度・ 0円・ 0円
寄附金・講座・研究部門 【 表示 / 非表示 】
-
スギ人工林内に更新した広葉樹群集の衰退状況-個体群動態パラメータと成長速度を用いた定量的評価-
寄附金区分:奨学寄附金
寄附者名称:住友財団 2007年12月
寄附金額:700,000円
-
孤立森林地帯に生息するニホンカモシカの環境選択性と森林群集構造との関係解析
寄附金区分:奨学寄附金
寄附者名称:住友財団 2001年01月
寄附金額:1,000,000円
-
スギ人工林内に更新した広葉樹群集の多種共存機構の解明
寄附金区分:奨学寄附金
寄附者名称:昭和シェル石油環境研究財団 2001年01月
寄附金額:350,000円
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
手入れ不足な針葉樹人工林の広葉樹林化:低コストな下刈り法の開発
学長裁量経費
資金支給期間 :
2011年08月-2012年03月研究内容 :
岩手を始め,日本各地で手入れ不足な人工林の環境保全機能低下が問題となっている。人口減少期で木材需要が減少する今日,人工林を広大に残す必要性は低い。そこで,手入れ不足人工林を伐採し,自然力を生かして低コストで広葉樹林化する技術が求められている。滝沢演習林を対象に,1) 有用広葉樹ケヤキの生育を妨げる雑草木の生育特性を解明し, 2) 初期成長の早い雑草木だけを刈り払う下刈り法を提案するのが本研究の目的である。1)では,ケヤキと種間競合する雑草木(タラノキやクサギなど)の侵入・成長特性を解明しようとした。2)では,ケヤキの枯死を引き起こす種間競合特性に基づき,できるだけ簡便な下刈り法を提案しようとした。
-
ニホンカモシカの生息環境を保全する森林管理計画手法の開発
学長裁量経費
資金支給期間 :
2009年06月-2010年03月研究内容 :
特別天然記念物ニホンカモシカの生息環境保全と林業を両立させる必要がある。滝沢演習林を対象に,1)カモシカの餌植物密度と収量比数等の説明変数との関係をモデル化し,2)森林管理シナリオ別のカモシカの生息環境を予測・評価する。
-
スギ人工林の林床植生分布を光・土壌水分・土壌窒素分布で説明できるか
学長裁量経費
資金支給期間 :
2007年08月-2008年03月研究内容 :
スギ人工林の林床植生分布を光・土壌水分・土壌窒素分布で説明できるかについて,パス解析や CCAを用いた多変量解析をおこなう
-
不成績なアカマツ天然更新地の改良試験−省力的森林造成技術の開発に向けて−
平成14年度北水会研究助成金
資金支給期間 :
2002年10月-2003年03月研究内容 :
所属学協会 【 表示 / 非表示 】
-
2023年05月-継続中
森林計画学会
-
2005年04月-継続中
森林立地学会
-
2002年01月-継続中
日本生態学会
-
1992年01月-継続中
日本森林学会
学会・委員会等活動 【 表示 / 非表示 】
-
2011年08月-2022年06月
日本森林学会 英文誌JFR編集委員
-
2009年09月-2011年06月
森林計画学会 IUFRO国際研究集会 監事
-
2008年04月-2014年03月
森林計画学会 監事
-
2008年04月-2014年03月
森林計画学会 編集委員
-
2008年04月-2011年03月
東北森林科学会 財務主事
学会活動 3(学会誌の編集・査読) 【 表示 / 非表示 】
-
Journal of Forest Research [査読 (2025年01月)]
-
Journal of Forest Research [査読 (2024年11月)]
-
日本森林学会誌 [査読 (2024年10月)]
-
日本森林学会誌 [査読 (2024年09月)]
-
日本森林学会誌 [査読 (2024年07月)]
マスメディアによる報道 【 表示 / 非表示 】
-
2015年度
岩手日報2月6日(土)6面「森林づくり効果確認 盛岡で県民税事業評価委」という記事にて、「岩手大学農学部の國崎貴嗣准教授が、森林整備事業の施工地のうち間伐から5年以上経過した96カ所の現状の分析結果を説明」と報道された。その内容について、さらに140字を費やして同紙面で紹介された。
報道区分: 国内報道(全国報道を除く)
メディア区分: 新聞
その他研究活動の特記すべき事項 【 表示 / 非表示 】
-
2007年度
2007年度中に論文査読を3件(J. For. Plann.を1件とJ. For. Res.を2件)担当した。
2007年8月3日付け岩手林業新報に「森林づくり県民税事業1年目の評価 國崎貴嗣氏が講演」という見出しの1面記事が掲載された。
国・地方自治体等の委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
東北森林管理局(林野庁)
委員会等名 : 令和6年度東北森林管理局技術開発委員会
役職名 : 委員長
2024年06月-2025年03月 -
東北森林管理局(林野庁)
委員会等名 : 令和6年度森林・林業技術交流発表会
役職名 : 審査副委員長
2024年06月-2025年03月 -
東北森林管理局(林野庁)
委員会等名 : 令和5年度東北森林管理局技術開発委員会
役職名 : 委員
2023年06月-2024年03月 -
東北森林管理局(林野庁)
委員会等名 : 令和4年度森林・林業技術交流発表会
役職名 : 審査委員長
2022年06月-2023年03月 -
東北森林管理局(林野庁)
委員会等名 : 令和4年度東北森林管理局技術開発委員会
役職名 : 委員
2022年06月-2023年03月
生涯学習支援実績 【 表示 / 非表示 】
-
森林 施業プランナー認定試験二次試験(森林施業プランナー協会)
種類 : 講習会
担当部門(講演題目) : 面接官
2024年11月 -
フォレストリーダー研修(宮城県林業労働力確保支援センター)
種類 : 講習会
担当部門(講演題目) : 森林整備部門の講師
2024年10月 -
フォレストリーダー研修(岩手県林業労働対策基金)
種類 : 講習会
担当部門(講演題目) : 森林整備部門の講師
2024年08月 -
岩手県立西和賀高等学校「森林環境教育」
種類 : 出前講義(高校・一般向け)
担当部門(講演題目) : 50分授業2回と野外実習(100分)
2024年08月 -
森林 施業プランナー認定試験二次試験(森林施業プランナー協会)
種類 : 講習会
担当部門(講演題目) : 面接官
2023年11月
産学官民連携活動 【 表示 / 非表示 】
-
ノースジャパン素材流通協同組合 皆伐施業ガイドラインの見直し検討会
実績年度 : 2020年度
活動区分 : 技術支援及び技術相談
-
相談者(アジア航測株式会社 環境部 森林環境課 小川吉平氏)
実績年度 : 2019年度
活動区分 : 技術支援及び技術相談
-
「いわて環境の森整備事業」施工地現地調査に係る打ち合わせ
実績年度 : 2019年度
活動区分 : 技術支援及び技術相談
-
国土防災技術(株)田中様
実績年度 : 2018年度
活動区分 : 技術支援及び技術相談
-
「いわて環境の森整備事業」モニタリング調査に係る打ち合わせ
実績年度 : 2016年度
活動区分 : 技術支援及び技術相談
他大学等の非常勤講師 【 表示 / 非表示 】
-
鹿児島大学
「温帯林概論」について,8月31日(水)の実地見学旅行を引率した。 ( 2011年08月 )
-
鹿児島大学
「温帯林概論」について,9月1日(水)の実地見学旅行を引率した。 ( 2010年09月 )
その他社会貢献活動の特記すべき事項 【 表示 / 非表示 】
-
2009年度
鹿児島大学開講科目である「温帯林概論」(FSCの澤口教員が非常勤講師発令されており,FSCの山本教員,農林環境科学科の青井教員,橋本教員,國崎が講義・実習を分担)について,9月2日(水)の実地見学旅行を引率した(10時から17時まで)。
-
2008年度
鹿児島大学開講科目である「温帯林概論」(FSCの澤口教員が非常勤講師発令されており,FSCの山本教員,農林環境科学科の青井教員,橋本教員,國崎が講義・実習を分担)について,9月3日(水)の実地見学旅行を引率した(10時から17時まで)。
-
2007年度
鹿児島大学開講科目である「温帯林概論」(FSCの澤口教員が非常勤講師発令されており,FSCの山本教員,農林環境科学科の青井教員,橋本教員,國崎が講義・実習を分担)について,9月5日(水)の実地見学旅行を引率した(10時から17時まで)。
-
2003年度
岩手木質バイオマス研究会運営委員
大学運営活動履歴 【 表示 / 非表示 】
-
2024年度
クラス担任
-
2024年度
附属産業動物臨床・疾病制御教育研究センター運営委員会/
-
2024年度
企画室特命班 (カリキュラム特命班)
-
2024年度
学科長・課程長
-
2024年度
点検評価委員会
その他大学運営活動の特記すべき事項 【 表示 / 非表示 】
-
2009年度
2009年5月26日から6月19日にかけて,卒業・修了時アンケート全学WGに参加した(会合1回,メール会議で計8回のメール送信)。本来,この WGは大教センター教育評価・改善部門会議委員(教務委員が併任)の担当だが,アンケートに明るくないとして,國崎に個人的に依頼された。教務委員会委員長と戦略企画・評価室室長で話し合ってもらい,國崎が農学部代表として対応することとなった。